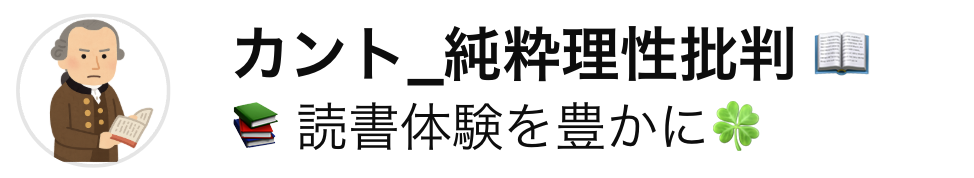本書(*)は、イマヌエル・カントが18世紀後半に著した哲学書であり、「人間の理性は何を、どこまで認識できるのか」という問いに根本から挑んだ大著です。カントはこの書で、理性が自らの限界を超えて誤った結論(形而上学的錯覚)に至ることを批判的に検討し、真に有効な知識とは「経験が可能な範囲内で得られる認識」に限られると説きました。
人間の認識には「感性(感覚的直観)」と「悟性(理解・思考)」という異なる働きがあり、これらが協力して初めて「経験」としての世界が成立するという見方は、哲学史上画期的な視点でした。とりわけ「コペルニクス的転回」と呼ばれる視座の変更――“認識が対象に従うのではなく、対象が認識に従う”――は、西洋哲学に多大な影響を与えました。